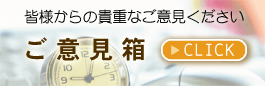‘ブログ’
春の甲子園
常総学院の応援で甲子園球場に着ました。球場には原田校長先生の同級生の丸山弁護士、参議院議員も駆け付けてくださり、アルプススタンドから選手にむけて一緒に声援を贈ってくれました。結果は何度か得点のチャンスが有りましたが、5回に先制された2点を跳ね返すことが出来ずに惜敗しましたが、グランドで一所懸命プレーする選手の姿やスタンドの応援団、チアリーディング、吹奏楽の応援する姿を見てると感動しますね!また、夏に甲子園に応援に来たいです。
荒川沖小学校卒業式
3月19日、私の母校である荒川沖小学校の第65回目の卒業式に出席しました。65名の卒業生は、4月から通う中学校の真新しい学生服に身をつつみ、緊張した面持ちで入場してきました。一人一人名前を呼ばれ、大きな声で返事をした後で、自分の将来の夢と、その夢を達成させる為には中学校で何をするべきかを壇上から堂々と後輩達や保護者の前で発表してから卒業証書を校長先生から受け取っていました。卒業生の皆さん、それぞれが描いた夢に向かって一所懸命頑張ってください。
平成25年3月定例議会一般質問
平成25年度第1回3月定例議会は5日に開会して議案の説明が行われ、11日より市政全般に関する質問、一般質問を行い、17名の議員が登壇しました。そして議案に対する質疑、各委員会で議案の審査が11日から14日の10時から18時まで行われ、21日の議会最終日にて採決を迎えることとなります。議会の模様は土浦ケーブルテレビで放映されます。また、インターネットでも議会の模様がご覧になることができます。私の一般質問の模様は、次の土浦市ホームページアドレスをクイックするとご覧いただけますので、http://www.tsuchiura-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=speaker_result&speaker_id=10
土浦市立博物館開館25周年記念
明日からの一般公開を控えた土浦市立博物館開館25周年記念「婆裟羅たちの武装・戦国を駆け抜けた武将達の甲冑と刀剣」の内覧会に参加してきました。展示は信長の台頭と題した第一章から第五章の武将たちの備えと題した五章で構成されています。また今回はカプコンから発売されているゲームソフト「戦国BASARA」とのコラボレーションした展覧会が実現しました。そして土屋藩ゆかりの刀剣「影法師」が展示されています。この「影法師」の経緯や展示品の説明を学芸員の皆さんが説明して下さいますので、百聞は一見に如かず、是非ご来場ください。
平成25年3月第1回市議会定例会
明日3月5日より平成25年3月第1回定例議会が開会いたします。本議会での議案は条例案件が21件、予算案件が11件、補正予算案件2件など49件の議案が上程され、審議されます。中でも最重要議案は平成25年度一般会計並びに特別会計予算です。一般会計予算は総額521億4100万円で、昨年度より7.2%増加しています。主な増加項目は、総務費が新庁舎整備事業や亀城プラザ改修事業費などで3.6%増、民生費が生活保護費や国民健康保険特別会計委繰入金などで2.6%増、土木費が宍塚大池周辺地区開発事業として土地開発公社からの買戻しと新治総合運動公園事業などで34.2%増、教育費が土浦小学校増改築事業や水郷プール再整備事業などで18.2%増となっています。主な増加は将来的なまちづくり事業の推進によるものなので、将来的な投資であり、それによる効果も期待されるところではありますが、民生費に関しては生活保護費などいわゆる扶助費の増加なので、今後も増加の一途をたどる可能性があり、この対策には頭を悩ますところであります。
さて、今議会で私が取り上げた一般質問は
1。「つちうらブランド」を推進するための施策についてお伺いします。
①「つちうらブランド」の定義について
②「つちうらブランド」の開発と認定について
③県との連携(茨城マルシェ)について
④国との連携(クール・ジャパン)について
2.違法薬物と類似した成分を含み、意識障害や呼吸困難など脳や身体に障害を起こす、非常に危険な「脱法ハーブ」から未成年者など人と地域を守る取り組みについてお伺い致します。
①禁止薬物としての指定や販売店の規制について
②脱法ハーブの危険性や知識の周知方法について
③薬物乱用防止教育の取組強化について
以上です。8番目の質問者と成るので、おそらく3月12日火曜日が質問の時間となると思います。議会を傍聴にいらしていただければ幸いです。
JRとの合同避難訓練
3月2日午前9時よりJR東日本と土浦市の合同で帰宅困難者を想定した避難訓練を実施しました。突風の吹く寒い天候の中、JR土浦駅下りホームからJR職員と土浦警察署の皆さんの誘導で帰宅困難者に扮した土浦市の関係者が一次避難場所となるウララ1まで避難路を確認しながら避難を実施しました。その後、県南生涯学習センターに於いて防災講演会が開催され、乙戸小学校で実施した地域と連携した学校の避難訓練の実例発表と市民防災研究所理事の池上三喜子講師による「まちを守る地域の団結力、深めよう互いの絆」と題した基調講演が有りました。会場は満席となる大勢の市民が参加され、講師のお話を深く頷きながらメモをとっていました。3・11以降、地域の防災意識が高まり、自主防災組織の結成や町内の避難マップや井戸マップなど積極的に取り組んでいる町内が増えているようです。土浦市でも地域防災計画の見直しを実施し改訂版が発行されると思います。災害はいつ起こるか分かりません。日頃の備えが一番大事である事を改めて学んだ防災講演会でした。
つくば市春日学園
文教厚生委員会でつくば市に平成24年に新設開校した春日学園の視察にお伺いしました。つくば市では平成20年より小中一貫教育に取り組み、昨年よりを市内全域で施設分離型を13学園、そして施設一体型の春日学園を開校しました。校舎は、一年生から四年生が学ぶ前期、五年生から七年生が学ぶ中期、八年生と九年生が学ぶ後期の三棟に別れ、教室は廊下を強化ガラスを使用した全面硝子扉で仕切られた明るい教室です。太陽光パネルを屋上に設置し、学校で使用する電力をまかなっています。校庭は400メートルトラックの広いスペースを確保し、サブグランドに芝生広場が有るなど素晴らしい環境の整った施設でした。授業も一年生から英会話やタブレット端末を使用するなど先進的な取り組みを拝見させて頂きました。ご多用中にもかかわらず、温かく視察を受け入れた、つくば市、春日学園職員の皆様に感謝致します。
熊本市小中一貫教育
行政視察三日目は熊本市立富合小学校と富合中学校で平成16年から取り組んでいる小中一貫教育です。教育目標を「21世紀の国際社会に貢献できる心身ともに豊かで逞しく、知性に満ちた個性ある子どもたちの育成」として、小1〜小4を前期、小5〜中1を中期、中2〜中3を後期に分けたカリキュラムで特色のある取り組みを行っています。視察は富合小学校にお伺いし、三角陽司校長先生のご案内で六年生の授業現場を見学させて頂いた後に、校長先生よりご説明を頂きました。英語の授業は、リズムにあわせてアルファベット順に単語を発声する発音の練習から始まりました。単純な英会話を通して発音を学ぶ内容では、LとRの発音の違いを聞き分ける等の英語を身近に感じさせる、まさに国際社会に貢献できることを目指した素晴らしい授業でした。富合小学校と中学校は約1キロメートル離れているため生徒同士が交流する授業等はそれほど多くは有りませんが、中学校の先生が小学校にて授業を実施するなどの指導者と生徒の交流が有るために、いわゆる中学ギャップが解消される 等のメリットが有ります。土浦市でも小中一貫教育の取り組みが始まりましたので、熊本市の取り組みを参考にさせて頂きます。
島原市地域児童見守りシステム事業
行政視察二日目は、人口約48000人の島原市です。島原市の視察項目は、平成19年に総務省からモデル事業として認可された地域児童見守りシステムです。この事業は、島原市内小学校全10校の校門等に、ICタグリーダーとWEBカメラを設置し、ICタグをランドセルに付けた小学一年生と二年生等を対象に、ICタグを読み取りと画像情報で登下校情報を把握するものです。小学校では、管理機能から登下校状況の把握及び履歴確認。登録した保護者はインターネットを経由しメール・画像で携帯電話やパソコンで確認できます。また情報提供システムでは、保護者や地域住民への情報提供を行い、安全確保を図るための参加を促進できます。導入時の総事業費が約8000万円で、年間約150万円保守管理費がかかります。登録者数は対象児童の約90%で、登録者にアンケート調査を実施したところ、約82%が必要性を感じ、約77%が事業の継続を希望している低学年の保護者には好評な事業であります。25年度がこのシステムの更新時期になるため、現在、事業予算や新しいシステムの導入を検討 しているそうです。本市でも市民の安心・安全を守ることは重要課題です。この事業を参考にして委員会でも議論して参ります。
文教厚生委員会行政視察
文教厚生委員会で 雲仙市「みずほすこやかランド」の視察に来ました。雲仙市は平成17年に7つの町が合併して出来た、人口約48000人の市です。この施設は合併前の旧瑞穂町時代に総額約18億円で整備された、ナイター照明付多目的グランド、テニスコート、プール、宿泊、宿泊などがある施設です。飛行機の遅れなどの影響で施設の到着が、予定より30分程遅れてしまいましたが、雲仙市議会文教厚生委員長さんをはじめ職員の皆様が温かく出迎えてくださりまりた。施設概要の説明を頂いた後に、施設見学を行いながら、委員会メンバーからの質疑に答えて頂きました。この施設は諫早湾に面した場所に有り、海を湖に変えれば、土浦市の霞ヶ浦総合公園と同じ様な感じです。東日本大震災の影響で使用不能に成った、土浦市の国民宿舎「水郷」の今後の方針や、新しい施設に生まれ変わる事が決定した「水郷プール」などに取り入れる部分や施設運営の問題点など大変参考になる視察でした。雲仙市の皆さん視察を引き受けてくださり誠にありがとうございました。
« Older Entries Newer Entries »